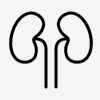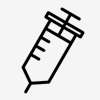「健診で尿蛋白が引っかかった」
「尿が泡立つようになった」
そんな経験はないでしょうか?
尿検査の異常は自覚症状があまりないことが多いです。
しかし、中には放置すると腎臓の働きが悪くなってしまう病気が隠れていることがあり、適切な検査や治療を受けることが重要です。
本記事では、蛋白尿について腎臓専門医が解説します。
蛋白尿って何?
蛋白尿とは、文字通り尿に蛋白質が混ざっている状態のことです。
通常であれば尿に蛋白が混じることはありませんが、腎臓に何らかの異常があると蛋白尿が出ることがあります。
蛋白尿が少量であれば自覚症状はないことが多いです。
大量に蛋白尿が出ていると、尿の泡立ちや足のむくみとして現れることがあります。
放っておくとどうなる?
健診で行う尿検査では、尿蛋白の程度に応じて(ー)(±)(1+)(2+)(3+)などと結果が出ます。
尿蛋白が(1+)以上でている人は(ー)の人と比べて、腎臓の機能が低下して透析になってしまったり、心臓や血管の病気に罹りやすいことが分かっています。
そのため、尿蛋白を指摘された際には、病院を受診し尿蛋白の原因を調べるとよいでしょう。
蛋白尿の原因は?
蛋白尿の原因は大きく分けて3種類です。
生活習慣に関連するもの
高血圧や糖尿病、肥満などが原因となります。
免疫が関連するもの
IgA腎症をはじめとする慢性糸球体腎炎、血管炎に伴う急速進行性糸球体腎炎、全身性エリテマトーデスに伴うループス腎炎、微小変化型ネフローゼ症候群、膜性腎症などです。
いずれも免疫の働きが関与している病気です。
病気ではないもの
起立性蛋白尿といって、運動後などに一時的に尿蛋白が出る病態もあります。
病院ではどんな検査をする?
まずは詳しい尿検査をします。
健診で行う尿検査は試験紙法という検査方法ですので、蛋白尿の具体的な量までは分かりません。
尿生化学検査という検査で、具体的にどれぐらい尿蛋白が出ているかを調べます。
また、これまでの経過や尿蛋白の量に応じて、疑わしい病気に関する血液検査をします。
腎生検といって、腎臓の一部を針で採取して顕微鏡で調べる検査が必要となることもあります。
蛋白尿の治療は?
蛋白尿の治療は、原因によって異なります。
起立性蛋白尿などの病気ではないものの場合は、特に治療は必要ありません。
高血圧や糖尿病などの生活習慣病が関連している場合は、それぞれの治療をしっかり行うことが蛋白尿の治療となります。
糸球体腎炎やネフローゼ症候群の場合は、蛋白尿を減らし腎機能を保護する薬に加え、副腎皮質ステロイドや免疫抑制薬の内服が必要となることがあります。
まとめ
蛋白尿は腎臓からのSOSです。
腎臓の機能が悪化する前に、適切な検査や治療を受けることが重要です。
蛋白尿を指摘されたら、ぜひ一度腎臓内科を受診しましょう。